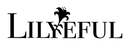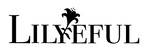日本人として「生き甲斐」を説明してほしい、
そう頼まれた時に、ズバリこれが生き甲斐です!という明確な概念はないんじゃないと。
日本の考え方、神道や禅はかなり特殊でその考え方が欧州で人気になり、広がって
日本に逆輸入して脚光を浴びるというのは最近良くある話。
IKIGAI、WABISABI、TEA CEREMONY、BONSAI、、、
でも日本人としての考え方が骨の髄まで染み込んでいる私たちと
捉え方も違ってきたり、本質がズレて伝わる事広がることも少なからず。
例えば今回の「生き甲斐」
"Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life"
(日本人の長生きと幸せな人生の秘密)
海外でこの本が出版されたのは2016年で
当時BBC等でIKIGAIのコンセプトが紹介されたりで、この本は大人気に。
現在の日本流行りにも伴って、このワードを知っている外国人はとても多い。
日本語でも「生き甲斐」と調べると
フレームワークが訳されて上がってくるけれど
これを作ったのはイギリス人の実業家。
わかりやすく、多くの人に伝えるには良いフレームワークかもしれない。
(フレームワークについては、「生き甲斐」をググってみてね)
けれど、生き甲斐はこのフレームワークが完璧にバランスが
取れていなければいけないものではないし
完璧なバランスが取れた仕事を見つけるためでもない。
個々が自分の経験、考え方を通して
何に価値を見出すのか、幸せを見出すのかであって
必ずこのフレームワークに当てはまる必要性はない。
私はどう生きたいのか?と問い続け、積極的な生きがいを持つ人もいれば
日常の中の小さな習慣や自分の中のある種、儀式が生きがいになる場合もある。
この場合は消極的生きがいとも言える?
庭いじりが生きがいになる人もいれば、ボランティアが生きがいになる人もいる
そして今はっきりとした生き甲斐がないからといって、それが決して悪いことではないし
生き甲斐があるから、良い!というそこに良し悪しも優劣もないということは忘れないでほしい。
こうすぐ仕事やお金が絡んでくるのは、凄く欧州的な考え方だな〜と。
アメリカ人は何事もビジネスにするのがとても上手だからね
(皮肉でもあり、皮肉ではないよ笑)
例えば、ヨガに関してもそうなわけで、
もちろんビジネスにすると、多くの人に触れられるようになるし学ぶ人も増える。
でもその反面、本質とはズレまくったものが登場する場合もある。
日本語が話せない人にとっては、日本の考え方、文化の「本質」に触れるのは
とても難しいこと。
例えば海外に旅行をしても、日本語で出てくる情報と、英語で出てくる情報と
また現地語で出てくる情報は全く違ったりする。
それと同じで本当にその国のことを知りたければ、
その言語を知らないとたどり着けない場所がある〜う
言語は文化だから。
プラス今は誰でも情報を発信できるからこそ、てっきとうな無責任は情報も溢れているしね笑
鵜呑みにしないことも大事よね
と情報リテラシーの話になりそうなので、この辺で。
さて、あなたは生き甲斐をどう捉えていく?
Love, yurina